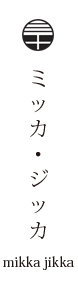岩山陽平 -夜空 -

和食に合う器が欲しくて、オンラインショップ巡り。
そんな時に出会ったのが、岩山陽平さんの「夜空シリーズ」でした。
届いた器は、その名の通り、まるで空の深い青がそのまま閉じ込められたような、印象的な色合い。
落ち着いた深い青は、盛り付けた料理をぐっと引き立ててくれそうです。
さて、この器には、何を盛り付けようか──。
サラリーマンから陶芸家へと転身された岩山さん。
陶芸家・橋本忍氏のもとで修業を積んだのちに独立し、現在は北海道・札幌を拠点に活動されています。
そのインスピレーションの源は、きっと広大な北海道の大地と空。
夜空シリーズの器を眺めながら、そんな想像を巡らせるのもまた、器との豊かな時間の一つです。

北海道といえば、馬鈴薯。
単純な私は、そんな連想から、これからの季節ならではの新じゃがを手に取りました。
岩山さんの深い青の器が、今夜の和食をさらに魅力的に見せてくれるに違いありません。
岩山 陽平
2013年、北海道・札幌に窯と工房を構え独立。
優しいカラーのマーブルシリーズや、深みのある青緑の夜空シリーズなどを中心に器を製作。
Korios Textiles - 使うほどに好きになる織物 -
記憶には殆ど残っていないけれど、私の父方の本家は田舎の機織り工場だったそうだ。ただ、その工場の近くで祖母が下宿を営んでいたことは、比較的よく覚えている。というのも、その下宿には大量の着物の端切れがあって、私は祖母からそれを少しわけてもらっては、せっせと人形の服を縫っていたからだ。もう一つ、記憶に残るのは、下宿裏の川で洗われる着物の生地たち。今となっては、それは滅多に目にすることのできない、なんとも素敵で風情がある光景。そうした出自が理由かどうかはわからないけれど、毎日大量の布に囲まれて仕事を続ける大の布好きとなった。
そんな布好きな私の娘も、お酒の飲める歳を迎え、深緑に蝶の柄があしらわれた振袖をまとった。小柄な私が着ていた時よりも、更に小さく切り詰められたその着物は、とある人形師の方がデザインしたものだそう。大人になりたての若者が集う場所では、「ちょっとシブすぎるんじゃないか」と夫は言うけれど、私のお気に入りだったその着物を、ウン十年の時を経て娘が引き継いでくれたのは、なんとも感慨深い。
今年の春、ある布に一目惚れした。Koriolis Textilesの手織りの布たちだ。迷うことなく、手に取ったのは、丁寧に織り込まれた、リネンのグーズアイ柄のショール。柄の一つひとつが信じられない程に繊細で、そこから溢れ出る作り手の想いが感じられる。
気が遠くなるほどの時間と手間がかけられているあろうことは言うまでもない。
作り手自らがインド藍で染め上げ、その糸で織り込まれた布もまた優しく美しい。自然素材と見事に調和したその色合いは、主張しすぎず、毎日の暮らしに溶け込むよう。日常の中で自然と育っていく、そんな布と言えるだろう。
時間をかけて染められ、織り込まれた布たち。その味わいと愛着は使い込む程に増していく。布好きでなくとも、自然と大切に使い続けたくなるというもの。こんな私はといえば、いつの日かグースアイ柄のショールを娘へと引き継ぎ、素敵なアンティークリネンへ育てることを企てている。

作家Profile/ 田中 香
・東京生まれ、在住
・エスモードジャポン東京校卒業
・縫製の仕事をしながら織りを学ぶ。
・2017年Koriolis Textilesとして制作活動を開始。
使うたびに心を楽しませてくれる、使うほどもっと好きになる、をコンセプトに、自然素材を中心に愛着を持って長く使えるものを制作しています。
シンプルなデザインに手織りならではの温かみと美しい色。
ほとんどの製品が自宅で手洗い等できますので、お手入れしていただきながら長くご愛用いただけます。
さまざまなことが交差して織りなす毎日の暮らしにコリオリテキスタイルの手織りの品を。
Tellur工房 - 火にもかけられる器 -

何がキッカケだったのか、思い出そうと頑張ってみても出てこないのは、「歳のせい」だと思いたくない。
一年ほど前、我が家には「本格的なドイツパンが食べたい」というブームがやってきた。それがあるとおぼしき方々のベーカリー、スーパーなどを訪ねてみては件のパンを買いあさり、「これはイマイチ」だとか「やっぱりドイツパンはこの酸味がいいよね」だとか御託をならべる。もっとも、私がドイツへ訪れたのはポルトガルへの旅の途中。乗り継ぎ便に間に合わず、トランジットで過ごしたほんの一晩だけ。本場のドイツパンなど食べた記憶はない。
さて、ドイツ語圏の寒い季節にはグリューワイン(Glühwein)と呼ばれる飲み物がよく飲まれるそうだ。
特にクリスマスマーケットで人気のこの飲み物は、赤ワインにシナモン、クローブ、オレンジピール、砂糖などのスパイスを加えて温めたもの。Tellur工房の片口ポットへ赤ワインを注ぎ、スパイスなどを入れて温める。それをそのままテーブルに運べば、食卓に温かな香りが広がる。

そんな温かい飲み物を片手に、酸味の効いたドイツパンをかじりながら待つのは、ザワークラウトキャセロール(Sauerkrautauflauf)。Tellur工房のキャセロールにジャガイモ、ザワークラウト、豚肉、ベーコン、玉ねぎなどを重ねる。生クリームと卵で作ったソースを塩、胡椒で味を調え、上からかけたらシュレッドチーズをたっぷり散らしてオーブンへ。あとは、こんがりと焼きあがるのを待つだけだ。
美味しい料理と飲み物、そして楽しい会話が続く食卓。そこを彩ってくれるのは、調理器具でありながらも、そのまま器としての存在感を放つTellur工房の作品たち。和食にも洋食にも馴染み、温かい料理をそのままテーブルに運べる、そんな「器」があるおかげで、我が家のドイツパンブームはまだしばらく続きそうだ。
作家Profile/ 陶芸家 小川佳子
神奈川県出身。大学で建築を学び住宅設計・インテリアデザインを仕事としましたが、卒業後に始めた陶芸に魅了され 2006年 Tellur工房(テルルコウボウ)を設立し陶作家としてスタートしました。
日常使いの器を制作し、 個展、クラフトフェア・企画展への参加、店舗への卸し、オンラインショップ等で発表しています。
日々の暮らしの中で「考えること」「作ること」「使うこと」を通して「あったらいいな」を作っていきたいと考えています。
そんな器が使い手の日常に溶け込み「いつもの器」となってくれたら嬉しいです。
伊藤由佳 - 経年変化を楽しむ装身具 -

2024年の初夏、緑が鮮やかな高原でのクラフトフェア。実はこのイベントにかかわらず、気分転換を言い訳に、この地へはよく訪れます。
いつもながらの心地よい空気を満喫しつつ、そのイベントを楽しんでいると、ふと気になる装身具が。一見柔らかな雰囲気ながらも、一方でしっかりとした力強さがとても印象的。そんな作品が気になり、作家さんにお話を伺ってみると、とても柔らかな印象ながら、なにか一本筋の通ったようなものが感じられました。
なるほど、作品には作り手の思いや個性が表れるものなのだなと、ひとり納得したのです。

「アクセサリー作りを始めたのは、ただ"好き"という気持ちから」と伊藤さん。でも今では、その素材そのもに魅了されているのだそう。
「真鍮のさまざまな表情が好き」と彼女は言います。磨き具合やデザインによって、その輝きや質感が変わり、時間が経つとまた違った魅力が現れる。指輪などは、使っているうちに自然とピカピカになったり、くすんできたり。それが逆に味わい深く、その変化も楽しみの一部なんだそうです。
制作過程では「なんか違うな」と思った瞬間を大事にしながら、試行錯誤して形にしていくそう。そんな柔軟な考え方と作品へのこだわり。そんな彼女の姿勢が、作品に独特の柔らかさと強さを与えているのかもしれません。
経年変化によってさらに素敵になるその装身具たちは、長い時間をかけて持ち主と共に変わり続ける。
伊藤由佳さんの作品は、そんな「一緒に成長する」楽しみを感じさせてくれます。
Kanade Copper-世代を超えて受け継いで行きたい道具-

とあるクラフトマーケットを歩いていたときのこと、数多くのブースが並ぶ中でひときわ目を引く作品に出会いました。素朴でありながらも独特な造形は、他のどの製品とも違う魅力を放ち、自然と私の目と足を止めさせました。「使い続けるとこうなっていくんです」と見せていただいたのは、何年も使い込まれたご飯炊き銅釜PAN。使い込まれた風合いの美しさ、手にずっしりと伝わる重み、その存在感に圧倒されました。
周囲を見回すと、そこには同じものが二つとない唯一無二の品々。一打一打丁寧に打ち鍛えられたその作品は、それぞれ異なる個性を放ち、使い手に特別な価値を提供してくれるはずです。まさに世代を超えて受け継いでいきたい一品。この素敵な出会いに、心躍らせながら帰路についたことが思い出されます。

Kanade Copper
工房から聞こえてくる トンテンカンテン・・・ その音と共に、我が家の暮らしはあります。 暮らしの中から作られるKanade Copperの作るモノは、 用と美、そして遊び心を大切にしたいという想いをカタチに。 できるだけシンプルな作りを心がけ、修繕しながら 長く使えるものを。 家族のレシピを子どもが受け継ぐように、次の世代へ そのレシピと一緒に手渡される道具になりますように。 作品ではなく、作り手から使い手に手渡され、 気取らず、暮らしに馴染んでいく” 日々の道具 ”でありたいと感じています。
Profile / オクダ クニヒロ 1968年広島に生まれる。少年の頃から甲冑に興味を持ち、金工を学ぶ。その後伝統工芸での修業、NYでの製作経験を積んできた時間が、ものづくりの礎となっている。気分転換に、ケーキやタルトを焼く時間が至福の時。
インド・ジャムダニ織

ジャムダニ織は、インド亜大陸の豊かな織物文化の中でも特に魅力的な存在です。そのルーツはバングラデシュのダッカ地方にあり、ベンガル地方全体に広がりました。17世紀のムガル帝国時代から、高級感と美しさが高く評価され、王族や貴族に重宝されていたそうです。しかし、産業革命による機械織りの普及と共に、この伝統的な手作業の織物は衰退の一途を辿りましたが、熱心な職人たちの努力により、その価値が再評価されています。
この織物は、製造過程が非常に複雑で時間を要するため、熟練した職人の手によってのみ作り出されます。生地に浮き出るように施される細かいデザインが特徴で、これは織りながら模様を作り出す「縫取り」の技術によって成されています。その技術は一般的に家族や師弟関係を通じて伝えられ、世代を超えて受け継がれてきました。ジャムダニ織の職人たちは、この伝統を守り続けることで、文化的なアイデンティティと誇りを保っています。ジャムダニ織を作る過程は非常に手間がかかり、一枚のサリーを完成させるのに、数週間から数ヶ月もの時間が必要とされることもあるそうです。
また、ジャムダニ織の生地は、その柔らかさと軽さで知られています。高品質のコットンを使用し、緻密な手作業によって織り上げられるため、肌触りが非常に滑らかで、通気性に優れています。これにより、暑い気候でも快適に着用することができ、特に夏のファッションアイテムとしてその価値は高まります。
この貴重な織物は、その美しさと高級感から、サリーやクルタ、スカーフなどの衣類に使用されるだけでなく、インテリアアイテムとしても活用されています。その繊細な織りと模様は、ただ飾っているだけでも美しく、インドの伝統的な美を現代の生活にもたらしてくれるでしょう。
このように、ジャムダニ織はその歴史、技術、美しさにおいて、単なる織物を超えた芸術作品と言えるでしょう。現代においても、その伝統的な価値を守りつつ、新しいデザインや用途で進化を続けています。この貴重なインドの文化遺産を、暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。